 パパナース
パパナース造影剤についてのお話です。
造影剤と言っても種類や、特徴など様々です。
今回は特に使用頻度の高いヨード造影剤について説明します。
アレルギー症状出現時の対応や、造影剤が血管外に漏れてしまった場合の対応方法など、看護する上で注意すべき点がわかります。


病棟勤務7年後、救急・外来業務を経験・DMAT隊員
看護師経験15年です。
得意分野:カテ看護・災害看護・マネジメント
2年前に株式口座を楽天証券で開設→積み立てNISAを始める。
月2万の積み立てで利益率30%。2年で50万円の資産運用に成功する。
最近では、積み立てNISAの限度額まで増額した(月3.3万円くらい)
それに伴い、s&p500や全米株式のファンドのみだったのを、J-REITや新興国株、TOPEX連動のファンドにも投資を始め、資産を分散している。
また、お小遣い程度の投資ですが、金や金鉱工業のETFやビットコインを少しづつ購入して投資の勉強を行っています。
造影剤って何?
- 造影剤の種類について
- 造影剤の特性と看護についてについて
- 造影検査で看護師が気をつける点
- まとめ


1.造影剤の種類について



看護師が絶対知っていて欲しいこと。
MRIとCTの造影剤は違うものですよっ!!!
CTではヨード系の造影剤というものを使用します。
MRIで使用するものは一般的にガドリニウムとかEOBなど成分が違う薬剤になります。
理由はMRIは磁力を使って撮影する検査で、撮影方法がCTとMRIでは全く違うからです。
カテーテル検査(心カテなど)や内視鏡(ERCP)で使用する造影剤も同じヨード系になります。
同じヨード系造影剤でも、血管内に投与するものと、胆管用、脊髄造影用など、投与ルートによって色々な造影剤があるので、間違えないようにして下さい。
2.造影剤の特性と看護について


ヨード系造影剤って体に入ると温かく感じます。
この反応は、個人差があるので、
「すごい熱くなる!」って人と「そうでもなかった。」って人がいます。
患者に説明する場合には、



CTを見やすくするために、体が温かくなる薬を血管からいれます。
で、大丈夫だと思います。
造影剤って粘性が高い液体(ネバネバしている)なので、基本的に37度くらいに温めて使用します。温めることで粘性が低くなるみたいです。
しかし、造影剤を使用して体が温かくなるのは別に薬を温めているからではないらしい・・・
詳しくは、浸透圧の問題とか難しい話なのでここでは置いておきます。
知りたい人は放射線技師に聞いてみて。
私は造影剤を入れるときは



体が頭からお尻まで温かく感じます。造影剤がちゃんと体を巡っている証拠ですね。
おしっこが漏れたような感じがする事がありますが、すぐに治まりますので安心してください。
と説明しています。
CTの場合は造影剤って静脈投与なので、注入して撮影すると、血管がよく見えるようになるんですが、血流が豊富なところはより温かく感じやすいみたいです。



すぐに治まります。通常の反応で心配はいりません。安心してください。
と説明してあげてください。
これも、造影剤の注入スピードによって変わります。通常の造影検査よりダイナミックスタディの方が熱く感じます。
3.看護師が造影剤で注意しなければならないこと
看護師が造影剤を使用する検査や治療で注意する点は2点。
血管外漏出とアレルギー反応です。


血管外漏出について
私の病院では、看護師が血管確保(静脈路確保)を行っています。
検査前に看護師が前室で血管確保を行います。
穿刺場所は、右手の正中皮静脈です。可能なら尺側正中皮静脈が第一選択となります。
理由は万が一造影剤が血管外に漏れた時に神経や血管を圧迫してしまう
コンパートメント症候群になりにくいからです。
もちろん、血管が入りにくい患者さんには他のところも穿刺しますが、第一選択は肘の所の血管になります。
針は20Gを基本としています。理由は造影剤がドロドロしているからです。
造影剤は触ってみるとわかりますが、触るとベタベタしています。
あんな、液体を1分くらいで100mlも血管に入れるんだから結構な圧力がかかります。
そのため、出来るだけ太めの針で血管確保します。
ただ、ルーチンの撮影であれば、血管確保が難しい場合には22Gでもできます。
さらに実際、血管確保がどうしても難しい場合にはダイナミックスタディでも、22Gで、何とか行ける事が多いです。その際は、放射線技師などに一度確認はしたほうが良いと思います。
20Gを無理して入れて、不安定な状態であれば、22Gでもしっかり静脈内に入っているほうが漏出は少ないと思います。
100%の確率で血管外漏出を起こさないということはまず不可能です。
大切なことは、予防と対策です。
造影剤を注入する前に、10mlくらいの生理食塩水をテストインジェクションして、留置針の所にスリルを感じるかを確かめます。
スリルとは透析患者の血管で感じるザーザーってやつです。
生理食塩水をボーラスで(一気に)入れると血管にスリルを感じますのでそれを、確かめます。
もう1つは、血液の逆流です。
これについては、逆流がないから漏れている!
というわけでもないのですが、逆流がみられない場合、再穿刺が可能であれば血管を取り直したほうが良いと思います。
造影剤の注入が始まると「あと何秒でX線がでます。」というのが放射線技師は分かります。検査にもよりますが、大体60秒くらい。撮影方法によっては早いと10秒とかの場合もあります。
看護師はエックスが出ている時には患者から離れないといけないため、造影剤が入り始めたら悠長に確認している時間はありません。
きちんと血管に留置されているかは、造影剤注入前にしっかり確認を済ませましょう。
確認ができるまでは放射線技師に待っていてもらいましょう。
もし、血管外に漏れてしまったら撮影を中止して主治医や放射線科医師に相談しましょう。
コンパートメントが強い場合には、皮膚科受診などが必要になることもあります。
また、漏出部位を冷やすことも有効と言われています(冷罨法)。
大切なことは、漏出が分かったら造影剤の注入を止める事が大切です。
その時に焦ってしまうのではなく、起こりうることは全て想定して、的確に対応する事が看護師には求められています。造影検査の際の血管穿刺について説明します!
アレルギー反応について


大体どこの病院でも、造影剤を使用する際には同意書と問診票を医師が確認して検査を予約してきます。
当院では、喘息や心疾患などアレルギーのリスクが大きい患者には事前に予防薬(主にステロイドなど)を内服してから検査を行います。
しかし、これで100%アレルギー反応は予防できるわけではありません。
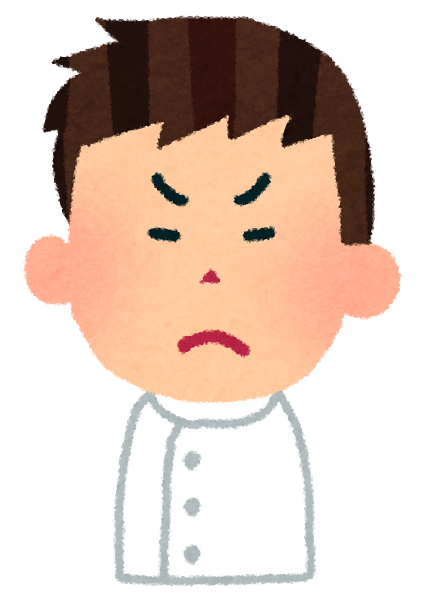
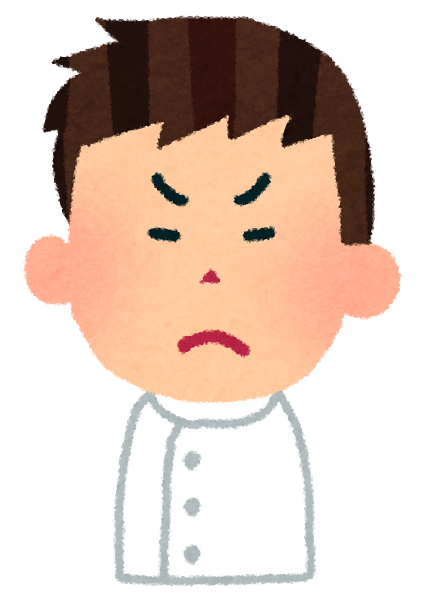
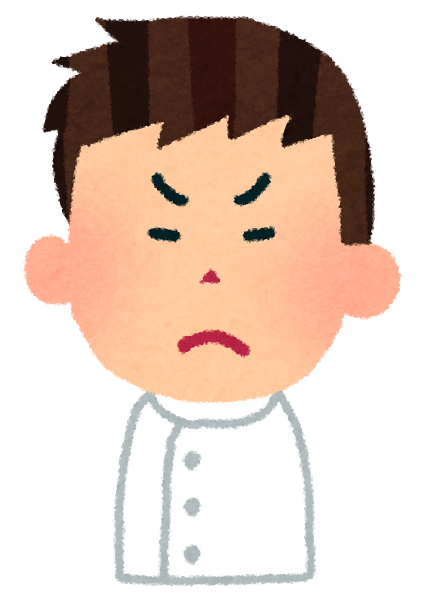
必ず、起こるかもしれない!!!
ということを念頭に検査を行わなければなりません。
重要なことは何回も検査を行っていて、今まで何ともない人でも突然アレルギー反応を起こすことがある!!!
ということです。みなさんは毎年花粉を吸っていても、ある日突然に花粉症を発症したりますよね。それと同じで、アレルギー反応は突然起こることも十分に考えられます。
症状も、様々ですが、放射線に従事している医療者はくしゃみ!
これがあると、「おやっ!!?」
と思います。くしゃみや痒み、鼻や喉の違和感から発症して
重篤なアレルギー様反応=アナフィラキシーショックに発展することはよくあります。
初期症状を見逃さないようにしてください!!!おかしいなと思ったら、放射線技師や医師に相談してください。
当院では造影検査後30分は院内での観察が必要になります。
それくらいアレルギー反応って恐いものなので注意してください。
急変に対応できるように、CT室には救急カートの準備が必要です。
また、多職種での急変時のシミュレーションの大切だと思います。
是非、参考にしてみてください。
4.まとめ
造影剤の代表的なものには、ヨード系とガドリニウム系の2種類がある。
ガドリニウムはMRIで使用する造影剤
ヨードはCTやIVR(心カテや胆のうドレナージ)などいろんな検査で使用します。
投与経路は、静脈内、動脈内など検査によりけりです。CTは主に静脈内投与。
造影剤を注入すると体が熱く感じる。
造影検査で看護師が気を付けることは血管外漏出とアレルギー!!!
どちらも、予防と早期の適切な対応が必要である。


いかがでしたでしょうか。造影剤についてざっくりですがお話させていただきました。
マニアックな分野なので看護師やっていても知らないことって多いと思います。
これからも、教科書的なことではなく、私自身が経験した内容を中心にお伝えしていけたらと考えています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
最後におすすめ図書を載せておきます。参考にしてみてください。
また、次の記事でお会いしましょう。
SEE YOU!!!!
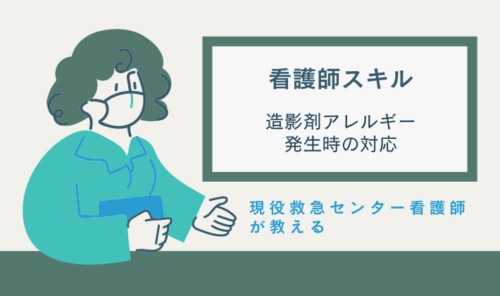
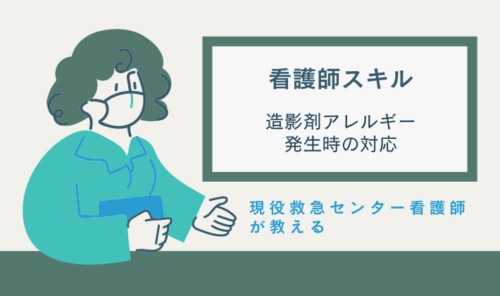
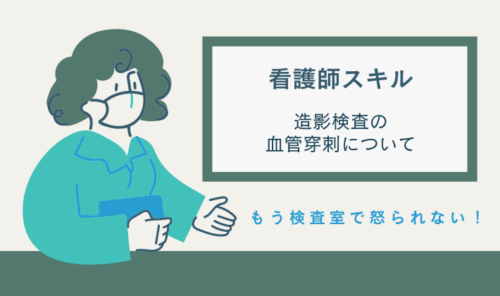
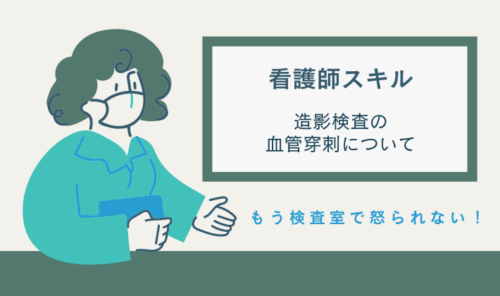
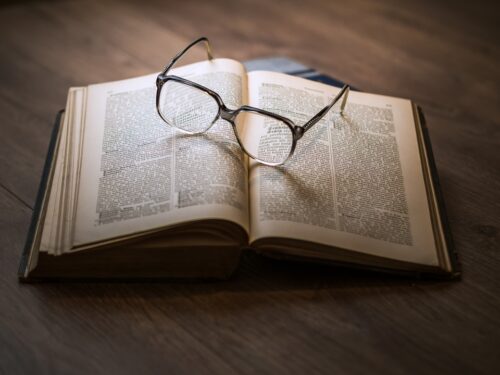
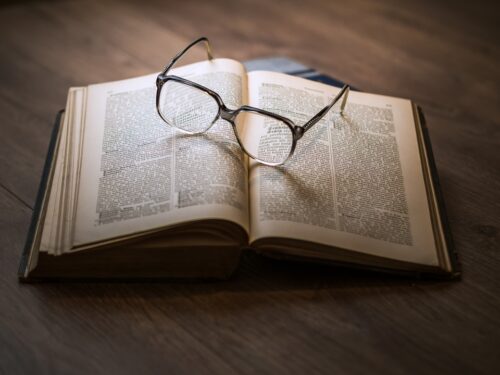









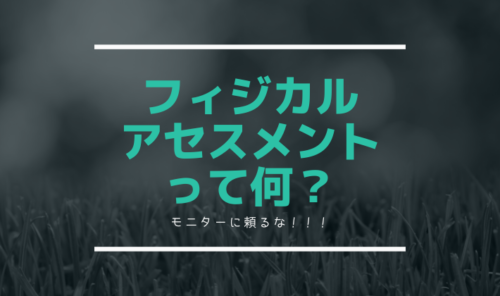
コメント