
DMATって何するの?災害現場に行かなくちゃいけないの?怖い!



コードブルーみたいな医療に憧れています!



DMATの仕事は災害現場に行くことだけではありません。むしろそれ以外の仕事が殆どです。
災害に備える。
いつどんな災害が起こっても対応できるようにシステムや教育を整えることもDMATの大事な仕事です。
今日はそんなDMATの業務についてお話します。
災害大国日本。
我が国は,その位置,地形,地質,気象などの自然的条件から,台風,豪雨,豪雪,洪水,土砂災害,地震,津波,火山噴火などによる災害が発生しやすい国土となっている。
世界全体に占める日本の災害発生割合は,マグニチュード6以上の地震回数20.8%,活火山数7.0%,死者数0.4%,災害被害額18.3%など,世界の0.25%の国土面積に比して,非常に高くなっている
http://www.bousai.go.jp/index.html
内閣府のホームページにも記載されています。2011年の東日本大震災。2016年の熊本地震。そのほかにも、台風や豪雨により毎年のように災害が発生しています。
DMATとは、災害派遣医療チーム Disaster Medical Assistance Team の略称です。
意外と知らない、DMATの世界をお伝えします。
ぜひ最後まで読んでみてください。
DMATの資格の取り方


災害拠点病院にお勤めの方は、ご存じかもしれませんが、
DMATになるには日本DMAT研修を受ける必要があります。
4日間の日本の研修が年に数回行われます。
場所は東日本(東京)と西日本(大阪、兵庫)です。
詳しくは厚生労働省DMAT事務局のホームページを参照してください。
http://www.dmat.jp/schedule/schedule.html
DMATの資格は、申し込んで受講すれば大体もらえます。
申し込みは個人ではなく、各病院毎に申し込みます。
4人組ぐらいのチームで参加することが多いと思います。
県によっては、ローカルDMATという制度があるところもあります。
ローカルDMATとは県単位で起きる災害に特化したDMATです。
通常のDMAT隊員は日本DMATといい区別しています。
ローカルは2日間の県の養成研修に参加します。
そこで、ローカルDMAT隊員の資格をもらえます。
ちなみに私は、ローカルです。
何が違うかというと、ローカルはその県の災害に特化しているため所属している県の災害事案にのみ招集がかかります。
また、技能を維持するための訓練も、基本的には県単位のものになります。
日本DMATの訓練も日本DMATと一緒であれば参加できることもあるみたいですが、私は参加した事はありません。
DMATの仕事


ローカルDMATになって、4年くらいなりますが、実災害には出動した事はありません。



DMATは興味あるけど、災害現場に行くのは怖いな。
と思っている方はよっぽどの事がなければいく事はありません。
私がローカルだからではなく、日本DMATも殆ど実災害現場に派遣されたことはありません。
さらに、強制では無いので、その時の状況で断ることもできます。
日赤などの災害特化型の病院でなければ、現場に出ることはほぼないと思います。
そのため、
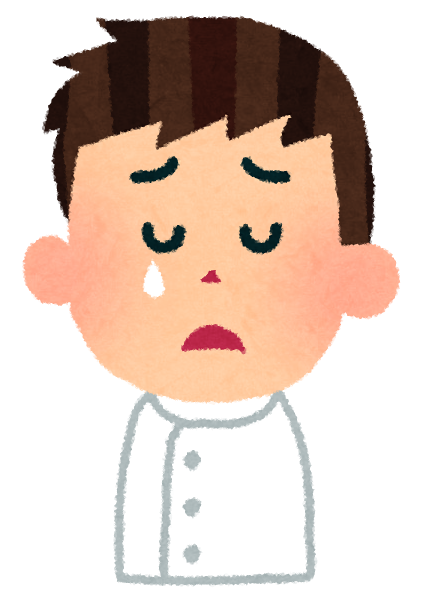
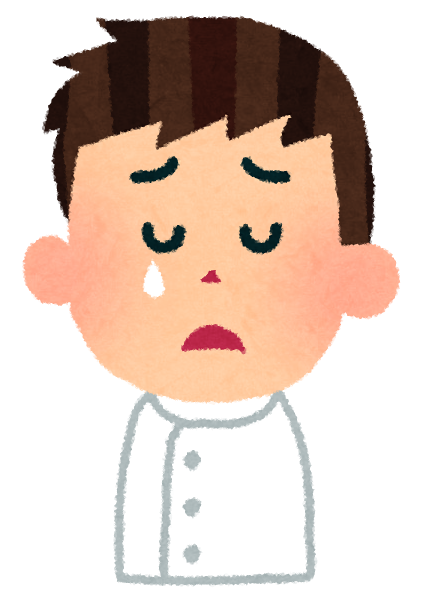
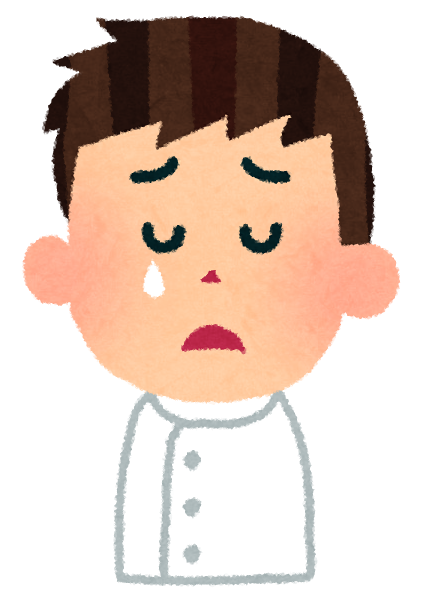
家族がいるからDMATはなあ・・・
という理由で迷っている方は是非1歩踏み出してみてください。
災害現場に行くことだけがDMATの仕事ではありません。
災害に備える仕事
災害時の患者を受け入れる体制を整えること
教育・育成
このような業務もDMATの大切な仕事の一つです。
主な業務内容


平時(非災害時)の業務について
メインは災害対策になります。
私の病院にはDMAT隊員が数十名います。
そのため、病院内のDMATの仕事を振り分けて行っています。
災害マニュアルの作成、訂正
災害訓練の運営
院内の看護師の育成
などが主な仕事です。
災害マニュアルの作成
病院内の災害マニュアルを作成・見直しをしています。私は看護師なので看護部の所を担当します。
災害マニュアルは災害発生時に
どこに院内災害本部を置くのか
本部のレイアウト
BCP(事業継続計画)について→水道・電気などのインフラ対策
職員の被災状況の確認方法
衛星電話について
など災害発生時にこれを見ながら動けるようにアクションカード的な要素も踏まえた使用になっています。
看護部のページには、
災害発生時に看護師がどこに集合するのか。
集合時に記載する名簿
赤・黄・緑・黒・トリアージポストに配置される看護師のリスト表
各ゾーンのリーダーの心得・動き方
各ゾーンのスタッフの動き方
トリアージタグの記載方法について
病棟のベッド状況の報告書
などが掲載されています。
このようなマニュアルを定期的に見直しています。
毎年担当がついているので、一応毎年見直していると思います。
病院全体の部分はロジが担当しています。
災害訓練の運営
私の病院では年に1回院内災害訓練を行っています。


毎回、その年のトレンドの災害などを踏まえて状況を設定して院内全体で行います。
行政(社会福祉事務所)や、近隣の病院と連携して行う大規模な訓練です。
DMAT隊員はその準備と運営を行います。
当日の午前中は災害本部の立ち上げの訓練
→偉い人だけが参加します。
災害発生に伴い、会議室に災害本部を立ち上げる。
災害マニュアルにそってレイアウトを作成する。
クロノロジーの作成
傷病者状況の把握
BCPの確認
午前中は災害発生から被災者が病院に運ばれるまでをシミュレーションします。
午前中の最後の方になると参加してくれる救命士が病院に到着します。
救命士は被災者を病院に搬送してくれる役や、患者の想定付与をしてくれます。
患者役は病院の付属の看護学生が演じてくれます。
患者にはDMATがムラージュという化粧をします。
これで、リアリティを演出します。
午後は実際に沢山のスタッフが集まり、被災者の受け入れ訓練を行います。
休日想定の場合、主に看護師は病院に着いたらまず、集合場所に集まります。
平日の場合は院内アナウンスに従い集合場所に集まります。
そこで、招集者リストに記名します。
このリストには自分が災害トリアージナースなのか?どこのゾーンでの看護を希望するかを記載します。
看護部長などの偉い人は午前中の内に、災害の種類や各ゾーンのリーダー看護師決めてあります。
集まった看護師をまとめ、各ゾーンに振り分けます。
希望のゾーンに配置されるかはその時の状況により変わります。
その後、実際に被災者が搬送されてきて皆さんがよく知っている災害訓練が始まります。
だいたい、1~2時間くらいの訓練をおこないます。
同じ時間に災害本部では、他病院のDMATが到着したり、行政と会議をしたり、
各ゾーンから上がってきた情報をまとめたり、
入院させたり、転院の手続きをしたりなど・・・
てんやわんやです。


その後、全体で集まり反省会を行います。
DMATはこのような災害訓練の運営と準備を行います。
半年くらい前から準備を始めます。
行政などと訓練日程を決定したりすることはもちろん。
災害訓練の目的の決定。
災害想定や患者想定の決定。
車いすやストレッチャーなど物品の確保。
点滴や酸素などの物品の準備。
患者に着せる衣類の準備。
救命士や学生に提供する弁当の準備。
災害マニュアルの確認。
看護師の育成と再教育
準備することは沢山あります。
それを分担して行っていきます。
大変な作業ですが、やりがいのある楽しい仕事でもあります。
院内看護師の育成
災害訓練の準備の所でも書きましたが、看護師の育成や教育も重要な仕事です。
DMATだけで、病院の災害対策はできません。
リンクとなる看護師が必要となります。
災害トリアージナースです。
当院では、院内認定の看護師を育成しています。
院内で2日間の日程で年1回養成研修を行っています。
また、技能維持として年1回技能維持研修を行っています。


PATトリアージやSTARTトリアージなどの実技を中心に振り返りを行っています。
JP-TECやITLSなどを受講しているスタッフではないので技能維持は大変難しいです。
そのため、まだまだ課題は多いですが、DMATを中心に少しずつ災害看護のスキルは向上していると感じています。
こちらも、継続が一番大切なことであると感じています。
まとめ


DMAT隊員になるためには、災害拠点病院に勤務する必要があります。
災害大国日本。
自分の身は自分で守る。
自分の大切な人を守れる知識と技術を身につける。
そのためにも、
興味がある方は是非一緒に災害看護を勉強しましょう。
ではまた。
SEE YOU!!!




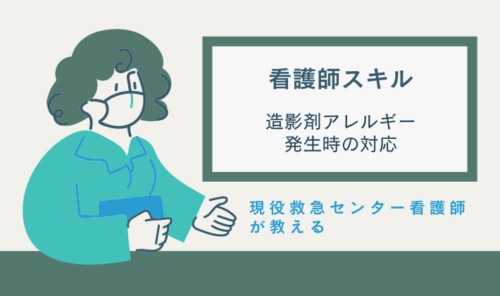





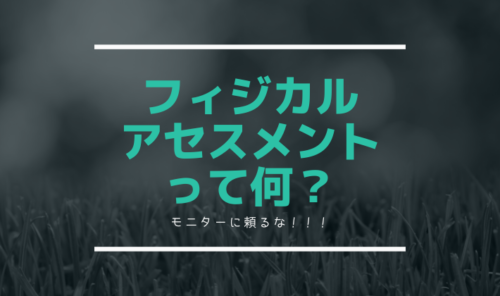
コメント