
病棟の看護師です。造影CTってよくやる検査だけど、何に注意して看護をしたらいいの?
どんな検査なんですか?
何で、留置してある針じゃなくて新たにルート取り直すのですか?



造影CTとは、その名の通り造影剤を血管内に注射してCTで撮影する検査です。造影剤を投与することで濃淡がついて血管などが良く見えるようになります。
注意点は血管外漏出とアレルギー反応になります。
造影剤は粘性の高い液体でドロドロしています。
その液体を自動注入器を使用して一定の量注入するため、留置針は新たに穿刺してもらう必要があります。
安全に検査を行うためによろしくお願いします。


看護師歴15年
病棟勤務7年後、救急・外来業務を経験
DMAT隊員
放送大学にて教養の学位を取得する。
院内のキャリアラダーでファシリテーターを行っている。
得意分野:カテ看護・災害看護・マネジメント・放射線科看護・内視鏡看護
病棟あるある
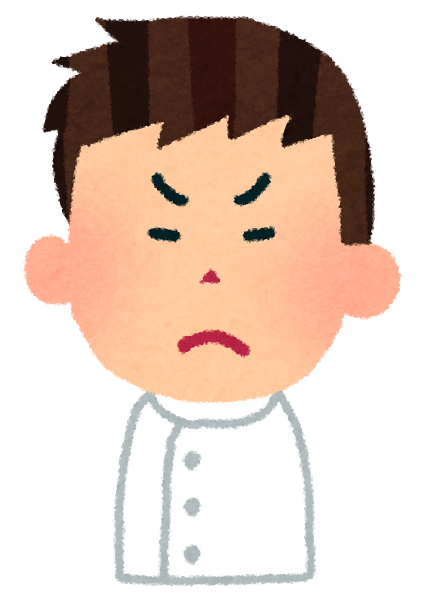
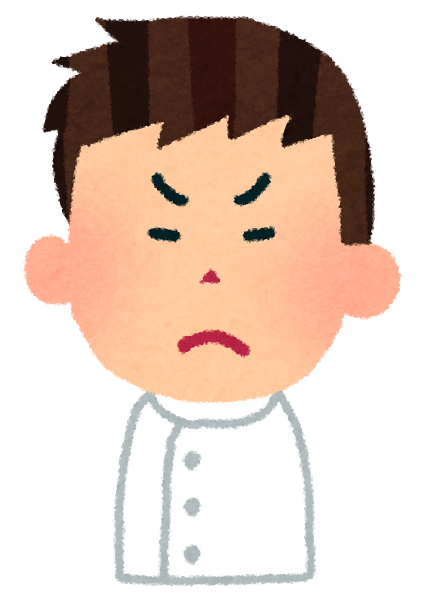
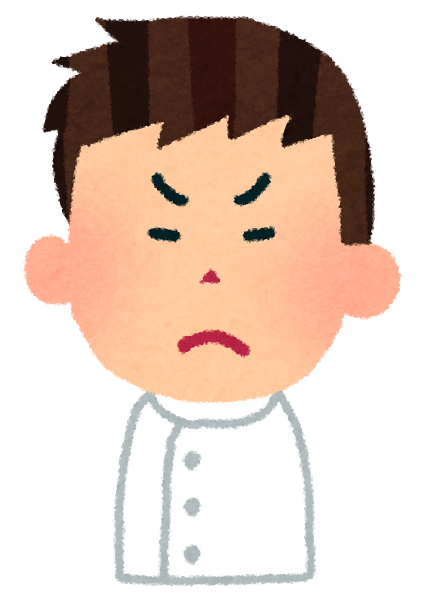
CT室に降ろして!
ってリーダー看護師に言われて、とりあえずCT室に降ろしたら



準備が全然できてないじゃん!



なんて検査室で怒られた経験ないですか?
この記事を読んで自信をもって検査に出せるようになってください。
どこに何ゲージで点滴挿せばいいの?


肘の静脈に刺しましょう。
できれば右肘静をお願いしています。
右の肘を刺す理由。
血管が太い
血管外に漏れたときにコンパートメント症候群になりにくい。
コンパートメント症候群とは?
コンパートメント症候群とは、コンパートメント内の圧力が異常に上昇する結果、そのなかに存在する筋肉や血管、神経などが物理的な圧迫を受けることから発症する病気を指します。
https://medicalnote.jp/diseases/
要するに、血管外に漏れた造影剤で神経や血管が圧迫され、神経障害や血流障害を起こしてしまうという事です。
わたしの病院では、大量漏出があった場合でも合併症を起こす可能性は低いため、基本として右尺側皮静脈を穿刺することにしています。


なぜ、左肘ではダメなの?
左肘静脈から投与した場合、心腔に到達するまでの距離が長くなります。
そのため、
造影剤到達時間が遅延する。
静脈内の造影剤がアーチファクトとなり、動脈の描出を妨げる。
3D画像作成時には、骨との分離が困難となる。
末梢に到達する造影剤のボーラス性の低下。
十分な造影剤が目的血管に到達しない可能性がある。
少し難しいですが
このような理由から、右肘を第一選択にして下さい。



入院中では、正肘では曲がってしまって点滴が落ちない



そんな時は気軽に検査室に相談してみてください。
何ゲージの太さの針で刺せばいいの?


これは、基本は20G~22Gがいいと思います。
血管外漏出防止のため翼状針ではなく、留置針(インサイト)を使用します。



なぜならば、造影剤は、ネバネバしているからです!
粘性が強い液体であり、注入方法はインジェクターと呼ばれる自動注入器で体内に注入します。
なぜ、こんな機械を使って入れるかというと、
造影剤は1秒間に何mlの造影剤を何ml入れる。
ということが決まっているからです。
総量とレートについては、その時の撮影方法によって異なります。
冠動脈や肺動脈などを撮影する場合には、1秒間に5mlぐらいの高スピードでネバネバ造影剤が体内に入ります。
そのため、なるべく太めの留置針で確実に穿刺する必要があります!
基本は22G針でも大丈夫ですが、ダイナミック撮影など条件次第では20Gでないと危険な場合があります。



造影CTは基本は20G針で!
無理は時は検査室に相談! と覚えておくと良いと思います。
おまけ情報 (造影剤が保温庫に入っている理由)
どこの病院も造影剤って加温庫っていう冷蔵庫みたいな機械の中で保管されていませんか?
あれは加温器と言います。
造影剤って温めた方が粘性は低下します。
粘性が低下したほうが、血管外漏出のリスクは少ないですよね。
そのために加温して保管しています。
必ず、キャップを開けたらすぐに使用しましょう。
造影剤が血管外に漏れてしまったら


造影剤は自動注入器を使って血管に注入することはお話ししましたね。
そのため、血管外に漏れていても、ドンドン押し込んでしまいます。
輸液ポンプと同じですね。
ただし!
もちろん安全機能もあります。
セキュリティアラームがあって、ある一定の圧力まで上昇すると注入が止まる安全機能もあります。
しかし、そこまでは、ドンドン押し込んで入れてしまいます。
そのため、なるべく太い針で確実に血管内に留置されていることが重要になります。
輸液ルートを使用する場合には、ロックが付いている耐圧のルートが必要になります。
尺側の肘静脈を穿刺する理由として、コンパートメント症候群を起こさないようにするため。
とありましたが、それは尺側の上腕は脂肪などの組織が多くスペースが多いからです。
それは漏出時にコンパートメントが起こりにくいというメリットではありますが、
同時に、スペースが多いために、造影剤が沢山皮下に入ってしまっても痛みや圧力が上がらず、血管外漏出を発見しにくいというデメリットでもあります。



造影する側の看護師はそのような事も知らないと行けません。
血管確保が困難な場合



そんなこと言っても20Gなんてとれないよ!
22Gでも可能な場合もあります。
血管穿刺が苦手な看護師もいますよね。
先ほども話しましたが、私の病院では、基本的な撮影では22Gで穿刺します。
しかし、ダイナミックスタディや3D撮影、冠動脈CTなどの撮影では、必ず20Gでのライン確保を行います。
なぜ、撮影方法によって穿刺ゲージが違うのか。
それは、先ほど書きましたが、
造影剤到達時間が遅延する。
静脈内の造影剤がアーチファクトとなり、動脈の描出を妨げる。
3D画像作成時には、骨との分離が困難となる。
末梢に到達する造影剤のボーラス性の低下。
十分な造影剤が目的血管に到達しない可能性がある。
撮影の種類によってどこの血管が観察したいのかが違います。
より早い層を観察したい場合は(冠動脈や肺動脈など静脈から投与すると直ぐにたどり着く場所)
造影剤を入れるスピードも速くなります。
そのため、同じ「CT造影」という検査でも撮影方法は違いがあります。
病棟の看護師さんはそこまで分からないと思います。
困った際には、放射線室やCT室に確認することをおススメします。
無理して太い針を血管確保が困難な患者に挑戦することも苦痛を与えます。
しかし、大切な事は基本は右肘に20Gです
20Gを入れることにはキチンとした理由がありますので、安全に検査を行うためにも正しい検査準備を心がけてください。
穿刺部位や穿刺針の選定については、病院によって違うと思いますので、各施設にて確認をお願いします。
ちなみに、血管穿刺が困難な場合
私の病院では、手背は使って造影はします。
しかし、下肢の静脈では造影はお断りしています。
理由は上で書いた理由とほぼ同じです。
踝(くるぶし)の所に24Gで留置している患者いませんか。
それは、さすがに無理です。
CVポートが入っている場合は、造影検査対応のパワーポートなら造影検査は可能です。
私の病院はパワーポートしか導入していませんが、ぞのCVポートが造影検査可能がどうかは確認方法がありますので、キチンと確認したうえで造影検査を行ってください。
造影剤が漏れてしまった場合の対処法
最後に造影剤が血管外に漏れてしまった場合の対処法についてお話しします。
基本は検査依頼医や読影医(放射線科診断医)の指示を仰いでください。
基本的なことは、
①造影剤の注入は直ちに中止する。
②漏出部位をチェックし、漏出量が少なく問題がない場合は再穿刺し再検査する。
③ある程度の量が漏れていると判断した場合、適切な処置を行い経過観察する。
④漏出量が大量であると判断した場合、皮膚科や形成外科にコンサルテーションする。
具体的に処置とは冷罨法になります。
冷たいタオルをビニール袋などに入れて、1回15~60分くらい冷やします。これを1日3回くらい。
1~3日程度続けます。
④では、漏出した量が50mlを超える場合には冷罨法など基本的な処置を行いながらコンサルテーションを検討して良いと思います。
まずは、医師や近くの放射線技師と相談してください。
まとめ
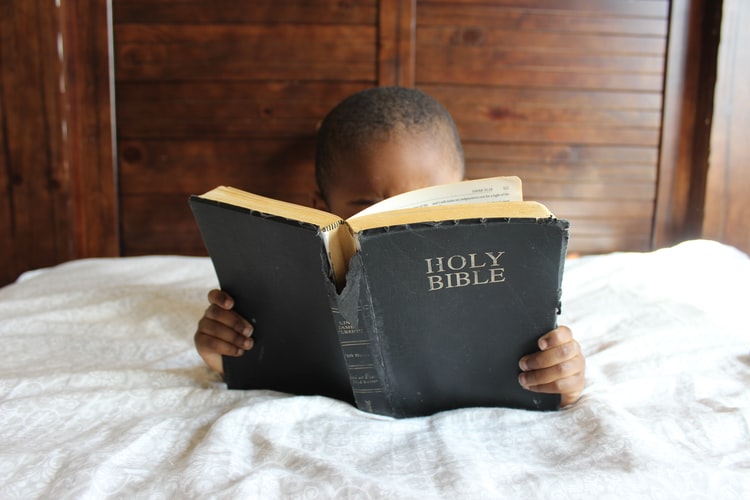
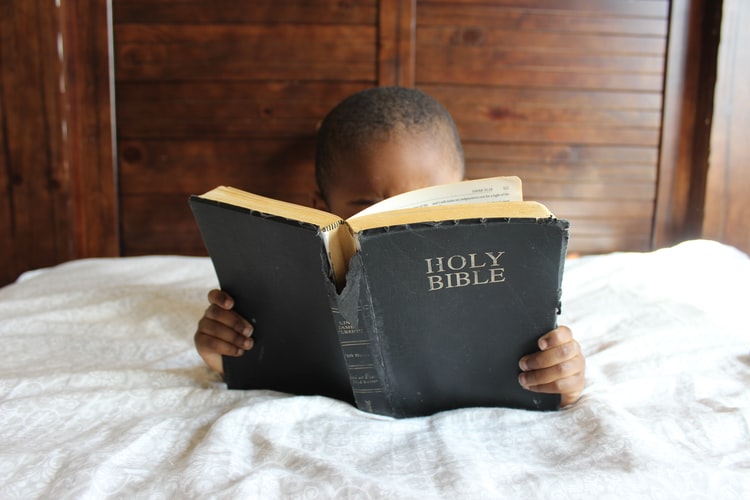
私の病院では、CT検査の際には生理食塩水100mlで血管確保します。
そして、検査台に横になった際に、
滴下が良好であるか。
逆血がみられるか。
テストインジェクションでスリルがみられるか。
(生食を10mlくらいシリンジで押し入れて血管に透析のシャントのようなスリルを感じるかテストする方法)
この3点を造影剤注入前に必ず確認します。
それでも、血管外漏出を100%予防することは無理です。
大切な事は早期の対応と適切な処置です。
安全な検査を行うためには他職種・他部署の連携が不可欠です。



私は病棟勤務で造影しないから関係ない!



処置版だから良く分からないけど、なんか先輩が検査降ろしてって言うからとりあえず連れていけばいいか。
ではなく、看護師としてキチンと考えて行動してください。
誰でも良ければ、別に看護師でなくてもいいんです。
連れていくだけなら、降ろすだけなら、看護助手でもいいんです。
看護師である理由。
考えてみてください。
最後にパパナースのおすすめの本を紹介します。1冊あると便利です。
ではまた。
SEE YOU!!!


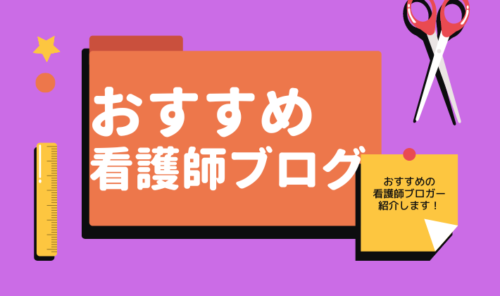
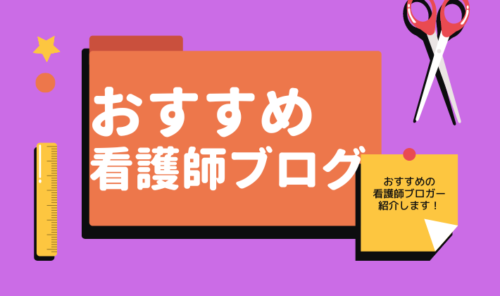



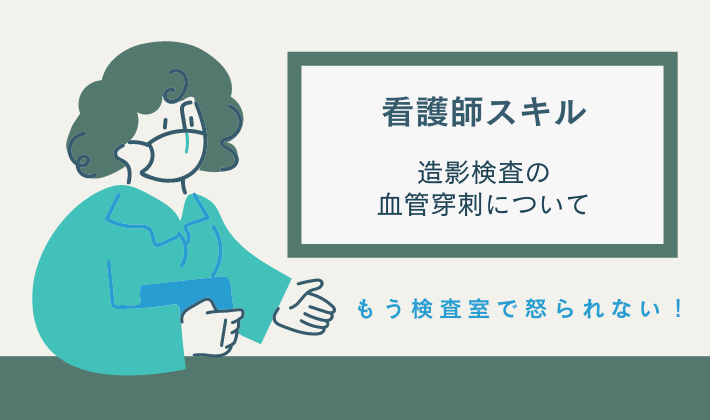


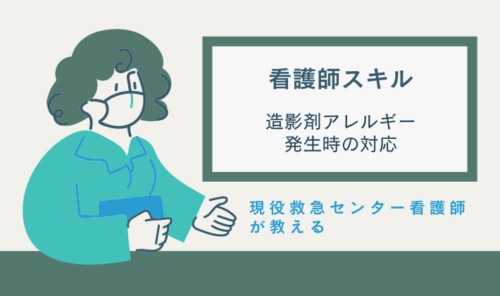





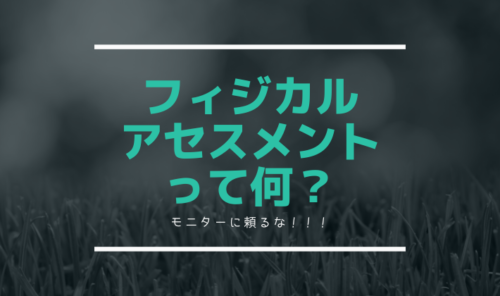
コメント